3.HSPの筆者の失敗談「1年半越しの後悔」

続いて、この記事を書くきっかけになった、筆者の失敗談を語っていきたいと思います。
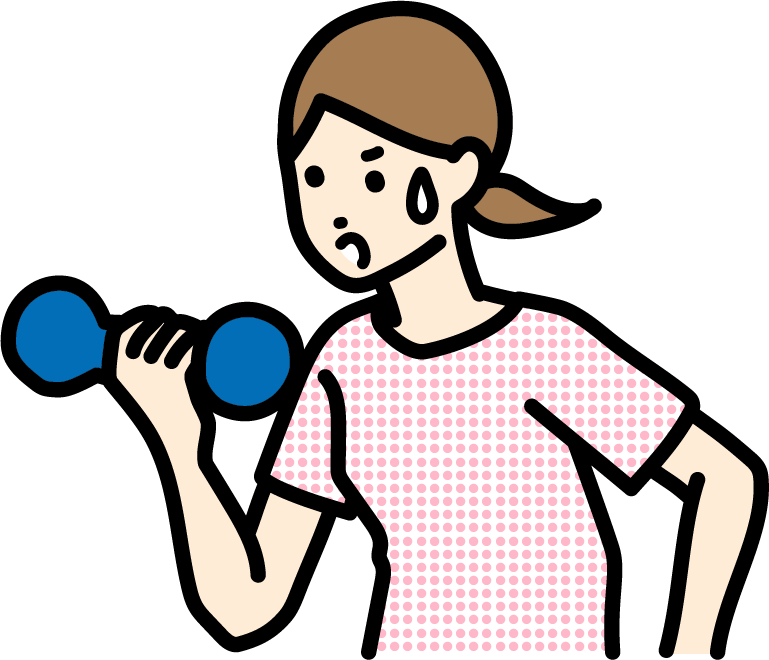 RAITA
RAITA私は断捨離をして、1年半後に急に後悔が来ました。
私はモノを収集したり、アーカイブするのが好きで、学生時代のモノも比較的残しておいていたタイプでした。
ただ、お金の管理をしっかりしようというタイミングとミニマリストの本やYouTubeを観て影響を受けたタイミングが重なり、「断捨離しなければ!」という強い思いに駆られて始めました。
当時、自分が何もできていないと思い込み、モノを捨てることで何かを達成できるような気持ちになっていたのだと思います。
その時の日記には「聖域なき断捨離」と書かれており、捨てることが目標になるという誤った進め方をしていたのです。衣類や書籍、もう読まないだろうと昔の日記なども捨てました。
それでも、断捨離をしてスッキリ感やお金周りの心配はなくなったことで満足できていました。
ただ、断捨離から1年半後に自分の中でメンタルが少し下がった時に、過去の日記を捨ててしまったことに対する後悔の念が浮かんできたのです。
その時分かったことは、人間は現在にいますが、過去や未来を行き来しながら生きているということ。断捨離に燃えていた時期は未来志向で、後悔の念が出てきたのは過去志向の時期だということです。
もちろん、人間は前を向いて生きるしかないのですが、過去や未来を行き来しているんだなと実感しました。
私は「今いらないものは捨てる」という基準で捨てましたが、「使わないモノでも在るだけで自分を形成しているモノ」も存在するということです。
私の場合は日記でしたが、皆さんも断捨離は慎重に進めてくださいね。
4.断捨離を行うステップ


最後に、私がオススメする断捨離のステップをご紹介します。
- 片付ける場所を決めスペースを確保する
- 決めた場所にあるものをスペースに全て広げる
- 広げたものを「必要」「不要」「保留」に分ける
- 「必要」なものをジャンル分けして収納する
- 「不要」なものを処分する
- 「保留」をどうするか考える
まず自宅の中をエリア分けします。キッチン、リビングなど部屋単位でも良いですが、オススメは、夏物の衣類や引き出し一段といった細かいところから始めることです。
片付ける場所にあるものを、確保しておいたスペースに全て広げます。これは、モノがどのくらいあるか全体量を把握するためです。
広げたものを見ながら、モノをざっくりと「必要」「不要」「保留」に分けていきます。
判断基準は人それぞれですが、私の場合は普段使うものは「必要」に。壊れたり汚れている、また数年使っていないモノは「不要」に。それ以外は「保留」に分けておきました。
分別後はまず「必要」なモノを収納していきます。ジャンルは「頻度」で分けると分かりやすいと思いますよ。引き出しやすい場所にはよく使うモノ、使う機会が少ないモノは奥まった場所にまとめて入れておきます。
続いて不要なモノを処分していきます。処分の方法は以下の通りです。
- 地域のルールに従ってゴミとして出す
- 不用品回収の業者に依頼する
- フリマアプリ・リサイクルショップを利用する
- 家族や親しい友人に引き渡す
処分が面倒くさかったり、フリマアプリで売れなくて結局家に置いてしまう人も多いと思います。処分は期限を決め、決断できたら早めに家から出したほうが良いでしょう。
「保留」のモノを時期を決めて確認しましょう。半年〜1年期間を置き、最初のステップのようにスペースに広げて確認します。もちろん、その前に必要と思えば取り出して使えば良いですし、必要な人がいれば譲っても良いでしょう。ただ、私の失敗談にも挙げたように「使わなくても在るだけで自分に存在価値があるモノ」もあります。迷った時は無理に捨てなくても良いのです。
まとめ
ここまで、HSPの人が断捨離で失敗しないコツと断捨離するメリット&デメリット、HSPの筆者の失敗談を踏まえて断捨離を進める6ステップをご紹介してきました。
HSPの人は「優先順位」を決めるのが大切と言われることが多いと思いますが、断捨離をすることにより自分を見つめることができ、自分の価値観が少しずつ見えてきます。
ただ、その時の感情によってはデメリットもあることも事実です。
自分と向き合いながらじっくりと断捨離を進めて、豊かな生活をお過ごしください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。








